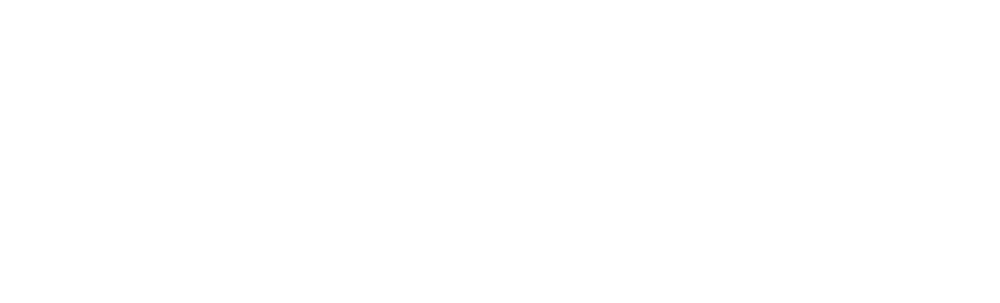

8/4 大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にて
『未来のおにぎり』のデモンストレーションと試食を行いました。
【当日の様子はこちら】
冷凍もち麦おにぎりのご購入はこちら
マルヤナギオンラインショップ
日本人が昔から食べてきた白米をにぎった「おにぎり」に
3種類の豆の「蒸し大豆」と「もち麦」を混ぜ込みました。
『未来のおにぎり』は私たちが直面している世界的課題を
おいしく解決していきます。
生活習慣病をはじめとした「健康課題」
「たんぱく質危機」と「環境問題」
社会・経済の持続可能性
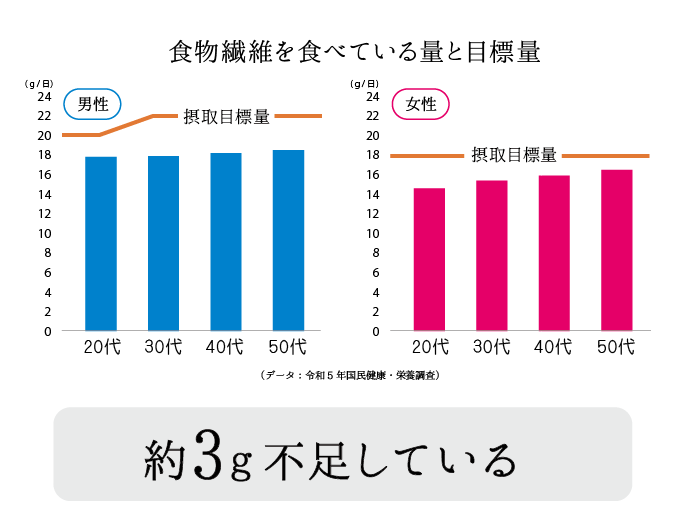
食の多様化で穀物や豆を食べる機会が減り、
食物繊維の摂取量が足りていません。
大豆は21.5g、もち麦は16.3gの食物繊維を含み(※)
このおにぎり1食で1日分の不足分を補うことができます。
※乾燥状態100gあたり(データ:日本食品標準成分表2020年版(八訂)、日本食品分析センター)

蒸し大豆は蒸しているからうま味と栄養の流出も少なく、
他の大豆製品と比較しても差はあきらかです。


世界的な人口増加、食生活の変化により、
将来、肉や魚などのたんぱく質が不足すると言われています。

蒸し大豆に含まれるたんぱく質は16.6g。
大豆は種まきから4カ月ほどで収穫でき
肉や魚に変わるたんぱく源として注目されています。
大豆は、牛肉に比べて生産に必要な水の量が1/8以下。
生産時に排出する温室効果ガスは1/85以下。
WWF(世界自然保護基金)の「未来の食材50」にも含まれています。
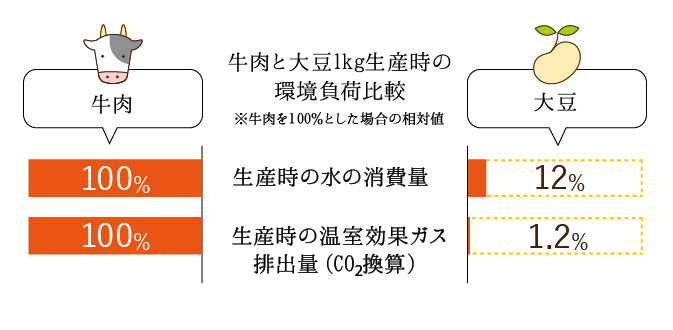
水の消費量データ:環境省バーチャルウォーター量一覧表より算出
温室効果ガスデータ:不二製油HPより(カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム数値より算出)
社会・経済の持続可能性には、
食糧の安定供給と地域社会の発展が不可欠です。

大豆は、気候変動や産地の実情を知り、
生産者と課題を共有することを大切にしています。
味に問題はないものの、割れなどで除去された豆も活用し、
限りある原料を大切にしています。

もち麦の産地では、もち麦が地域のイベントや食育に活用され
地域の食卓やお店で積極的に食べられています。
もち麦の栽培面積が拡がり、
持続可能な農業と地域活性化が進んでいます。

このおにぎりには、様々な世界的課題から
人類を救う可能性があるのです。
8/4 大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」にて
『未来のおにぎり』のデモンストレーションと試食を行いました。
【当日の様子はこちら】
冷凍もち麦おにぎりのご購入はこちら
マルヤナギオンラインショップ
